実は深い翻訳業界㊽~ 直すだけじゃ済まされない、AI 翻訳×ポストエディットの実情
- SIJIHIVE Team

- 2025年7月31日
- 読了時間: 6分
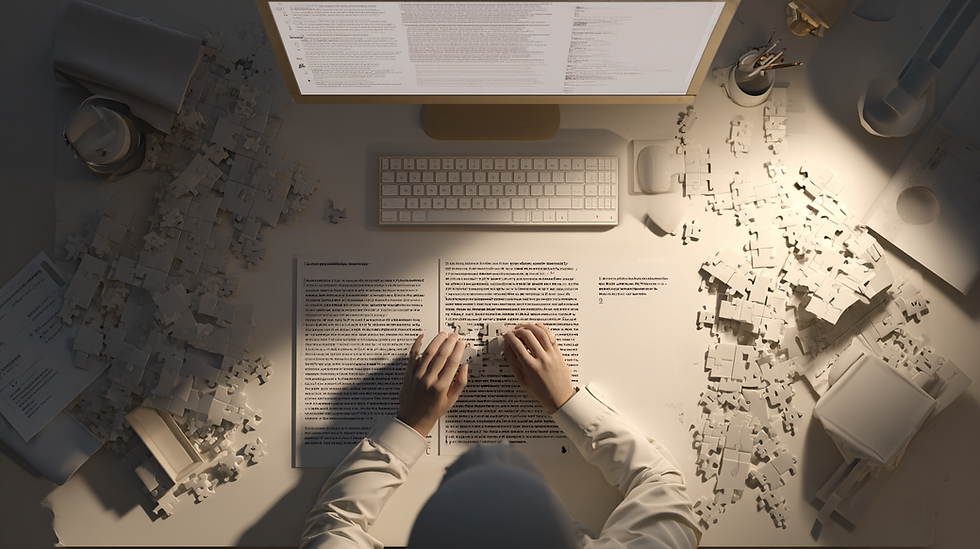
「AI で翻訳して、人間がちょっと直せばいいでしょ?」——そんな発注者の声を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
近年、このような考え方から“ポストエディット(PE)”という手法が注目されています。機械翻訳(MT)の進化により、低コストでスピーディな翻訳ができる―そんな期待が高まる一方で、実際の翻訳現場では「文脈のズレを直すのがかえって大変」「品質にばらつきが出る」といった声も少なくありません。
本記事では、ポストエディットの基本から、現場で直面する課題、そして意外とコストが下がらない理由までを整理し、翻訳者・企業双方にとって理解しておきたいポイントをお伝えします。
そもそもポストエディットとは?翻訳業界における位置づけ

ポストエディットの定義と背景
ポストエディットとは、AI や機械翻訳(MT)で生成された訳文をベースに、人間の翻訳者が品質を補正・調整するプロセスです。人間がゼロから訳す従来の「人力翻訳」と比べて、初稿の作成を機械が担うことで、全体の作業負荷を軽減しようとするものです。
近年は ChatGPT や Gemini といった生成 AI が普及し、さらに Phrase や Memsource などの CAT ツールの AI 導入も進んでいます。こうしたツールの台頭により、特にボリュームの大きい案件では、機械翻訳をベースにした編集が現実的な手段として選ばれることが増えてきました。
コスト削減になると言われる理由
翻訳を「ゼロから」行うのではなく、機械翻訳(MT)を下訳として活用することで、翻訳者が初稿を一から作成する必要がなくなり、作業時間や人件費の削減が期待されます。特にマニュアルや仕様書のように文型が固定されたコンテンツでは、機械訳でも一定の精度が出やすく、PE によって効率よく仕上げられるケースが多く見られます。
また、多言語での展開や短納期対応が求められる場面では、PE によって翻訳の大幅なスピードアップが期待できるという点も、企業にとって大きな魅力だといえるでしょう。
ポストエディットの現場で起きていること

“直すだけ”では済まされない、実務上の負荷
ポストエディットという言葉からは、「すでにある訳文をちょっと直すだけ」という印象を受けがちです。しかし実際には、MT による訳文が文法的に正しくても、次のような問題が含まれていることが多くあります。
・意味の取り違え
・文脈との不一致
・語調の不自然さ
・表記ゆれや用語の揺れ
結果として、文構造を一から見直し、文章全体を再構成するような手間が発生することも多く、実質的には“翻訳のやり直し”に近い作業になるケースも少なくありません。また、全体のやり直しに至らなくても、MT 翻訳の「間違い探し」のような修正が続くことで創造性を発揮しにくく、翻訳者にとっては精神的にも消耗しやすい作業となりがちです。
翻訳の目的によっては PE は逆効果になる
一見便利に見えがちなポストエディットですが、実はどの案件でも効果的だとは限りません。マーケティング資料、製品 UI、ブランドメッセージ、文学作品など、感情表現や語感が重視されるコンテンツでは、MT で細かなニュアンスを再現するのはまだ非常に難しいからです。
たとえば、ホームページ上に「Join Now!」というボタンがあったとします。 MT はデザインや用途などの文脈(コンテキスト)を把握していないため、場合によってはこれが「いますぐ参加しなさい!」と翻訳されてしまうことも。もちろんこのまま使うことはできないので人の目できちんと確認した上で、「今すぐ参加」や「参加はこちら」などよりやわらかくトーンに配慮された翻訳に修正していく必要があります。
このようなケースでは、翻訳者が事実上根本からリライトすることになり、結果的に作業量や納期が当初の想定を大きく上回ることも。コスト削減を目的としたはずの PE が、かえって逆効果になるリスクがあるのです。
品質と納期のバランスが崩れるリスク
PE を前提にプロジェクトを組むと、「短納期×低単価」で見積もられることが少なくありません。しかし、MT の出力品質は文脈やジャンルによって大きくばらつきがあるため、修正に時間を要し、かえって納期や品質に影響を及ぼすリスクがあります。
特に複数の翻訳者が関与する案件では、「どこをどの程度直すか」の判断基準が人によって異なり、訳文の統一感が損なわれるケースも。こうした事態を防ぐには明確な品質ガイドラインが欠かせませんが、「短納期×低単価」の条件下では、そこまで準備できないケースも多いのが実情です。
ここまででお伝えしてきた通り、実際の翻訳現場では、ポストエディットが必ずしも労力やコストを大幅に削減する手法とは言い切れません。むしろ「ポストエディット時代」の到来によって、翻訳者はこれまでとは異なる新たな課題に直面しているといえるでしょう。
では、どんなときにポストエディットは“あり”なのか?

PE に適した文書の特徴
ポストエディットが有効に機能するのは、定型文やマニュアル、FAQ、仕様書など、表現の繰り返しが多く、言い換えの余地が少ない文書です。たとえば、「〇〇をクリックしてください」などの命令文が多数含まれる操作ガイドなどがその典型です。
また、法的文書や医療系文書などにおいても、標準化された定型表現が多く使われている場合には、PE で一定の精度を確保できる可能性があります。このようなジャンルでは、MT の得意領域と人間による補正作業のバランスが取りやすく、用語の統一や処理の自動化が可能になるため、全体の翻訳効率を高めることができます。
運用のコツは「PE ありき」ではなく「最適手法の選定」
最近では、「まず PE ありき」でプロジェクトを設計するケースも増えていますが、常にそれが最適とは限りません。原文の特性や翻訳の目的に応じて、「PE」「完全自動」「人力翻訳」などの手法を柔軟に選定することが重要です。
この判断には、翻訳者やプロジェクトマネージャーの専門的な知見と経験が不可欠です。また、クライアントと翻訳者側との事前のすり合わせ──たとえば、スタイルガイドやトーン、用途の共有──も成果物の品質に直結します。
まとめ ― ポストエディットは万能ではない。その本質を見極めて

ポストエディットは、適切に運用すればスピードとコストの両面でメリットを得られる手法です。しかし「AI で訳して少し直せば済む」という考え方は、現場の実態とはかけ離れており、品質のばらつきやコストの増大といったリスクを招く可能性があります。
翻訳業務において大切なのは、文書の目的と内容を正しく見極め、「本当に PE が最適かどうか?」をプロの視点で判断すること。そして翻訳者やプロジェクト担当者との対話を通じて、最適な翻訳手法を選び取る姿勢が、成功の鍵を握っています。
AI 翻訳が当たり前になった今だからこそ、AI ありきではなく、文脈ありきの翻訳戦略が求められているのです。
=========================================
著者プロフィール
YOSHINARI KAWAI
2008 年に中国に渡る。四川省成都にて中国語を学び、約 10 年に渡り、湖南省、江蘇省でディープな中国文化に触れる。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、英語と地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。コロナ禍で帰国を余儀なくされ、現在は福岡県在住。
![実は深い翻訳業界[53]~「この翻訳、本当に効果ある?」投資対効果を最大化する翻訳プロジェクト管理の秘訣](https://static.wixstatic.com/media/16d396_4d2c6bca649f4d6d8c22456d54173102~mv2.png/v1/fill/w_980,h_549,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/16d396_4d2c6bca649f4d6d8c22456d54173102~mv2.png)
![実は深い翻訳業界[52]~ことばに“敬意”を込めるということ ― 翻訳者が意識すべき倫理とは](https://static.wixstatic.com/media/16d396_49131a0f5f93497b901c872080d318a3~mv2.png/v1/fill/w_980,h_549,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/16d396_49131a0f5f93497b901c872080d318a3~mv2.png)

コメント